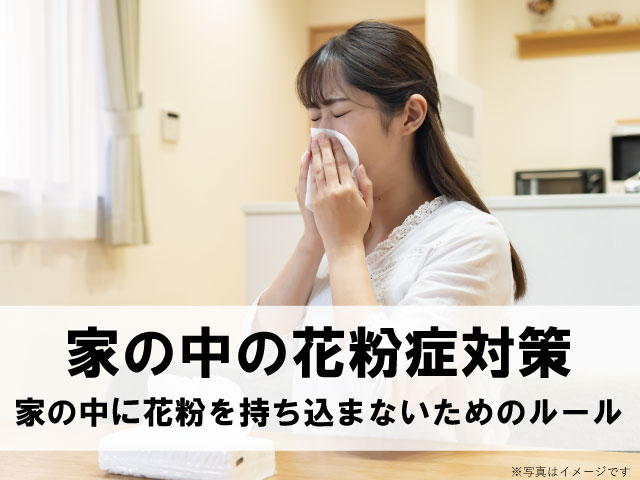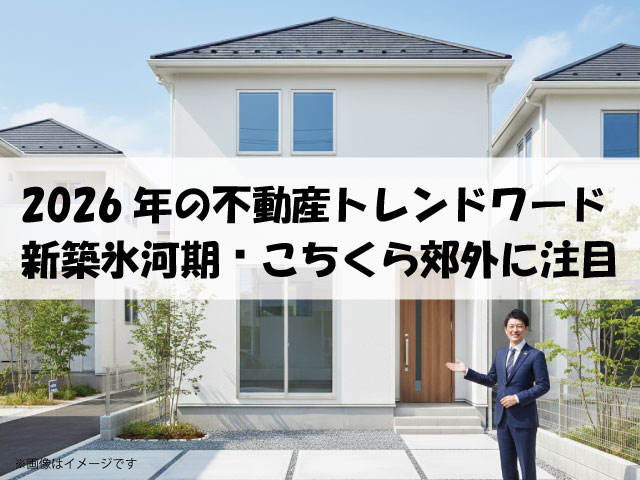Column
コラム
「老後破産にならない」住宅購入。40代からの住宅ローンと資金計画の考え方。
住まいのお役立ち情報 2025/07/24
本記事では、近年増加傾向にある40歳前後の方々の新築一戸建て住宅のご購入と、それに伴う住宅ローンのご利用について、老後の生活や資産計画にどのような影響があるのかを、国土交通省やフラット35利用者調査の資料に基づき考察いたします。
現在40歳前後で、これから住宅ローンを利用して物件のご購入をご検討されている皆様にとって、本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
住宅ローン平均年齢44.3歳:平均年齢は上昇傾と晩婚化の影響
住宅ローンを利用する方の平均年齢について、最新の調査報告書から詳細を見ていきましょう。
国土交通省が発表した令和5年度の調査報告書によりますと、住宅を購入された方の平均年齢はおおよそ40歳前後となっています。特に、一戸建て住宅を購入された方の平均年齢は38.2歳という結果が出ています。
一方、住宅金融支援機構の「2023年度 フラット35利用者調査」を見てみますと、住宅ローンを利用された方の平均年齢は44.3歳となっています。注目すべき点として、この平均年齢は2017年度から一貫して上昇しており、2023年度は前年度と比較して+1.5歳と、その傾向が強まっていることが分かります。この調査における平均年齢は、注文住宅、新築住宅、中古住宅といった全ての住宅種別を含んだものです。
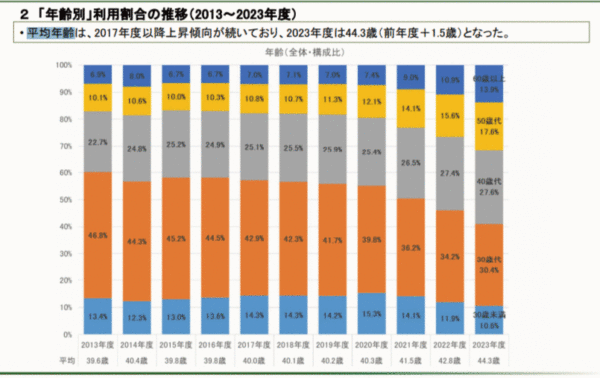
さらに、同調査によると、40歳代の住宅ローン利用率は、これまで最も高かった30歳代の利用率に匹敵する勢いを示しており、50歳代の利用率も徐々に上昇しています。
国土交通省の調査報告書をより詳しく見ると、分譲戸建住宅を購入する方の年齢は概ね40歳前後であり、そのうち61.6%の世帯が住宅ローンを利用しています。
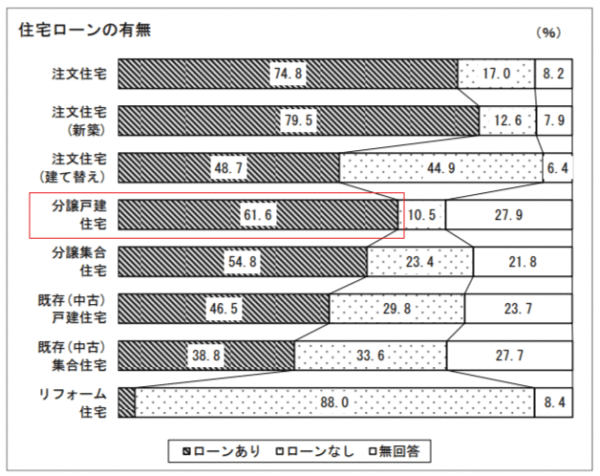
住宅ローンは一般的に、75歳や80歳までに完済するように計画されることが多いため、若いうちに住宅を購入し、返済期間を長く設定することは、定年退職後の返済負担を軽減する上で有効な手段となります。若い時期に購入するメリットとしては、返済期間を長く設定できるため、毎月の支払額を抑えられる点が挙げられます。しかしながら、若い時期はまだ収入が安定していない場合もあり、希望する金額の住宅ローンを組むことが難しいという側面もあります。
これらの理由から、住宅ローンを利用する方の平均年齢は、単に住宅を購入する方の平均年齢よりも高くなる傾向にあると考えられます。
また、社会全体として、住宅を購入する年齢は年々遅くなる傾向が見られます。
その背景には、晩婚化や晩産化といった社会的な要因が影響していると考えられます。厚生労働省の調査によりますと、令和5(2023)年の平均初婚年齢は夫が31.1歳、妻が29.4歳であり、第一子が生まれた時の母親の平均年齢は同じく令和5(2023)年で31.0歳となっています。この母親の平均初産年齢は、1995年(平成7年)と比較すると3.5歳上昇しています。
このように、結婚や出産の年齢が晩年化していることが、マイホームを購入する年齢が遅くなる一因となっていると考えられます。
≫関連記事「一戸建て住宅を買う人の平均年齢・分譲戸建住宅は38歳」
40歳で考える:分譲戸建住宅の購入価格例と資金計画
ここでは、40歳で建売住宅を購入する場合について、価格の例と資金計画のポイントを解説します。
■40代で住宅ローンを組むということ
一般的に、40代は20~30代よりも収入が増えやすく、ある程度の貯蓄がある方もいるでしょう。そのため、住宅ローンの借入可能額も増え、希望する物件を購入できる可能性が高まります。
ただし、住宅ローンの返済期間によっては、定年退職後も返済が続くことがあります。特に、お子さんがいるご家庭では、教育資金や老後の生活費の準備も考えながら返済計画を立てることが大切です。
40代はお子さんの教育費が最もかかる時期という方も多いです。教育資金や日々の生活費とのバランスをしっかりと考え、無理のない返済計画を立てましょう。もし、お子さんが既に学校を卒業している年齢であれば、お子さんの結婚費用やご自身の親の介護費用なども考慮に入れると良いでしょう。
■建売住宅の平均的な購入価額
「2023年度フラット35利用者調査」データによると、建売住宅の平均的な購入価額は次の通りです。
全国平均だと「3,603万円」ですが、地域により大きく差があります。
<建売住宅の所要資金>
| エリア | 所有資金(=購入価額) |
| 全国 | 3603.2万円 |
| 滋賀県 | 2,733.7万円 |
| 京都府 | 3,881.9万円 |
| 大阪府 | 4,007.1万円 |
資料:住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査」より作成
40歳、3,880万円の建売住宅購入を考える:資金計画の例
ここでは、40歳の方が京都府の平均価格である3,880万円の建売住宅を購入する場合を例に、資金計画の考え方を見ていきましょう。
資金計画で考えること
住宅を購入する際には、物件の価格だけでなく、諸費用と住宅ローンについて考える必要があります。
・諸費用: 物件価格の約6%~10%程度かかると言われています。3,880万円の物件の場合、約230万円~388万円が目安となります。これには、登記費用、仲介手数料(中古の場合)、保険料などが含まれます。
・住宅ローン: 原則として、物件価格を上限として、頭金や諸費用を差し引いた金額を借りることができます。返済期間や金利などを考慮して、無理のない返済計画を立てることが非常に重要です。
住宅ローンの計算例(フルローンの場合)
もし、3,880万円の全額を住宅ローン(フルローン)で、30年の返済期間で借りた場合を考えてみましょう。
ここでは、以下の条件を仮定します。
・購入する住宅: 新築住宅(ZEH水準省エネ住宅)
・扶養家族あり(19歳未満の子どもが1人)
・計算の参照: 借入額/3,880万円、変動金利/0.64%、返済期間/30年、金融機関/りそな銀行京都支店
・月々の返済額:約118,483円
①40歳現在:住宅ローン控除を利用(最大13年間、53歳まで)
住宅ローン控除を利用すると、年末のローン残高の0.7%が所得税(一部、翌年の住民税)から控除されます。この期間の控除額の合計は約280万円となる見込みです。これにより、毎月の実質的な負担が軽減されます。
この時点(2037年12月)の住宅ローン残高は約2,343万円となる見込みです。
②54歳:住宅ローン控除が終了
住宅ローン控除が終了すると、月々118,483円の満額を支払うことになります。
この年齢層では子育てが落ち着いてくる方が多いですが、お子さんの結婚費用や親御さんの介護費用、そしてご自身の老後の生活費など、必要に応じて検討することをおすすめします。
③60歳で定年退職した場合
退職後も住宅ローンの返済が続くことになります。70歳までの10年間、年金や貯蓄から返済していく必要があります。20年後の年末(2045年12月)の住宅ローン残高は約1,300万円となる見込みです。
この残高を考慮し、老後の生活費の準備も視野に入れた資金計画を立てることが重要です。
まとめ
上記の試算は、住宅ローンをご利用になる方の平均年齢や建売平均価格を基にした、あくまで一例のシミュレーションでございます。実際に住宅ローンをお借りになる金額や金利の種類、ご返済期間などによって、月々のご返済額や控除額は大きく変動いたします。ご自身の状況に合わせて、しっかりと資金計画を立てることが大切です。
お子さんを育てながら、住宅ローンのご返済やご自身の老後資金のご準備ができるかどうかご心配な方は、多くいらっしゃるかと存じます。当記事が、皆様が住宅ローンのご返済額やその割合、ご丁寧なご退職後の生活、そして老後資金についてお考えいただく一助となれば幸いです。
≫参照1:国土交通省「令和5年度 結果の概要(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/kekka.pdf)」
≫参照2:フラット35利用者調査2023年度(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/kekka.pdf)」
![]() 「
住まいのお役立ち情報 」の最新記事
「
住まいのお役立ち情報 」の最新記事