Column
コラム
【2025年版】新築住宅を購入するなら知っておくべき補助金やお得になる制度
補助金や制度 2025/05/09
※2025.5.9更新
マイホームの購入を検討する際、多くの方が悩まれるのが「お金」の問題ではないでしょうか。受けられる補助金や助成金、税金の優遇制度があれば、できる限り活用したいと考える方も多いと思います。
この記事では、2025年の最新情報をわかりやすくまとめてご紹介します。新築一戸建てや建売住宅をご検討中の皆さまに向けて、税金の軽減措置や住宅補助金制度について簡単に解説しています。ぜひ、マイホーム購入の参考にしていただければ幸いです。

【2025年】新築住宅購入を対象とした補助金・助成金制度一覧
| 1)戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
|
2025年度は「省エネ」と「脱炭素」がキーワード
2050年のカーボンニュートラル実現という国の大きな目標に向けて、住宅分野でも省エネ基準の強化が進められています。2025年には省エネ基準の適合が義務化され、2030年にはその基準がZEH水準に引き上げられる見込みです。こうした背景から、住宅をはじめとする建築物における省エネ(=脱炭素)は、今や国の重要政策の一つとなっています。
さらに、2024年元旦に発生した能登半島地震では、高齢化率や旧耐震基準の住宅が多い地域で甚大な被害が発生しました。このことを受け、国土交通省は「住まいの安全確保」や「住宅の耐震化」を、今後の重点施策として掲げています。
1)戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
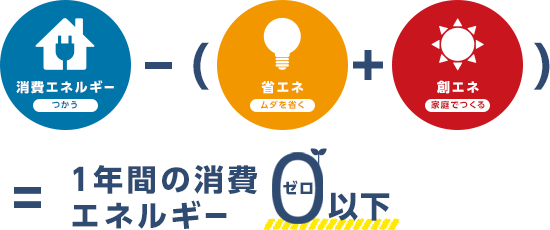
ZEHとは快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅の一次消費エネルギー量が正味で概ねゼロ以下となる住宅のことを言います。
「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」は、要件を満たす住宅を、ZEHビルダーまたはプランナーとして登録されている施工会社が新築すると補助金を受け取ることが可能な経済産業省・環境省による補助金制度です。(エルハウジングはZEHビルダーに登録しています。)
2025年度では、「ZEH支援事業」に55万円/戸、「ZEH+支援事業」に90万円/戸の補助が受けられます。
| 対象の住宅 | 補助額 |
| 戸建住宅のZEH | 55万円/戸 +α |
| 戸建住宅のZEH+ | 90万円/戸(前年より10万円減額)+α |
上記の戸建住宅ZEHおよびZEH+は、追加設備などにより追加補助が受けられます。
これから新築住宅の購入や住宅を建築される予定の方は、このZEH補助金について知っておくと良いでしょう。最新情報がわかり次第、コラムでご紹介させていただきます。
≫過去の記事「ZEHの住宅性能や補助金・助成金制度2024年度版」
≫参照 環境省HP「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 【令和7年度】(https://www.env.go.jp/content/000248499.pdf)」
2)子育てグリーン住宅支援事業

2024年の「子育てエコホーム」に代わり、2025年からは新たに「子育てグリーン住宅支援事業」が始まります。11月29日には、国からこの事業の創設に関する発表がありました。
「子育てグリーン住宅支援事業」では、省エネ住宅の新築や住宅の省エネリフォームを対象に、支援が行われます。特に注目すべきは、ZEH水準を大きく上回る「GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅」が新たに設定された点です。このGX志向型住宅に対しては、最大160万円の補助が受けられることとなっています。
制度の目的
| 国土交通省HPより
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化の支援を強化するため、国土交通省及び環境省は、「ZEH水準を大きく上回る住宅(GX志向型住宅)」の新築や、子育て世帯等を対象とする長期優良住宅やZEH水準住宅の新築を支援する新たな補助制度を創設し、賃貸住宅も含めて幅広く支援します。 |
▼対象の世帯・住宅・補助額
| 対象世帯 | 対象住宅 | 補助額 | |
| すべての世帯 | GX志向型住宅 | 160万円/戸 | |
| 子育て世帯等 ※1 | 長期優良住宅 | 建て替え | 100万円/戸 |
| 上記以外 | 80万円/戸 | ||
| ZEH水準住宅 | 建て替え | 60万円/戸 | |
| 上記以外 | 40万円/戸 | ||
※1:「18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)」
「GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅」は、環境負荷を最小限に抑えつつ、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの活用を重視した先進的な住宅です。この住宅は、2030年に義務化されるZEH水準を大きく上回る省エネ性能を備えており、すべての世帯が補助金の対象となっています。
一方で、「長期優良住宅」や「ZEH水準の住宅」については、子育て世帯・若者夫婦世帯(※1)が対象となります。
さらに、長期優良住宅やZEH水準の住宅では、住宅の建て替えかどうかによって補助金の額が変わる点も注目すべきポイントです。建て替えが必要な場合は、より手厚い補助が受けられる可能性があります。
「GX志向型住宅」は、高い省エネ性能と手厚い補助金が魅力であり、これから新築住宅を検討する際の大きなポイントとなるでしょう。環境に配慮しながら、経済的なメリットも得られるため、これからの住宅選びの重要な選択肢となりそうです。
〈参照元〉
≫国土交通省HP「住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定!(https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001249.html)」
≫国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業の概要 12/27更新(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001846078.pdf)」
3)減税制度
新築住宅の購入においては、補助金や助成金制度だけでなく、減税制度も利用することができます。減税制度を活用することで、大きな節約が期待できるため、事前にどの減税制度が利用できるかを調べておくことが非常に重要です。
①住宅ローン減税・控除
住宅ローン減税(正式名称「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを利用して新築、取得、または増改築を行った場合に所得税の控除を受けることができる制度です。この制度では、年末のローン残高の0.7%を所得税から最長13年間控除できます。また、控除の一部は翌年の住民税に適用されることもあります。
ただし、この13年間の控除を受けるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。特に、対象となる住宅には一定の性能や基準が求められ、所得制限も設けられています。2024年からは、省エネ基準適合住宅以上の物件でないと住宅ローン控除を受けられないため、新築住宅を購入する際には、その物件が省エネ基準に適合しているか、また「建築確認の日」なども合わせて確認することが重要です。
▼控除率:各年末の住宅ローン残高の0.7%(2025年度・令和7年 入居)
| 対象の住宅 |
借入限度額 | 控除期間 | |
| 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 左記以外 | ||
| 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |
| その他の住宅 (省エネ基準を満たさない) |
0円 ※2023年末までに建築確認を受けているものは借入限度額2,000万円
|
10年 | |
昨年までの措置として実施されていた住宅ローンの残高上限の拡充が、子育て世帯や若者夫婦を対象に、2025年の入居分まで延長されることになりました。
具体的には、子育て世帯が長期優良住宅などを購入する場合、住宅ローンの残高上限が5,000万円まで認められ、入居から13年間で最大455万円が所得税などから控除される仕組みとなっています。これにより、住宅取得に伴う経済的な負担が軽減され、子育て世帯がより安心してマイホームを取得できる環境が整えられます。なお、住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。適用を受けるための手続きを忘れずに行い、控除制度を有効に活用しましょう。
≫関連記事「2025年住宅ローン減税 子育て世帯等に対する控除の拡充」
②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長
住宅取得環境が悪化する中、住宅取得に係る負担の軽減及び良質な住宅の普及を促進するため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等を3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日))延長されました。
父母や祖父母などの直系の親族から、子や孫に住宅取得資金などを贈与する場合、そのうち一定金額について贈与税が非課税になる特例です。
通常、親などから贈与を受けると、基礎控除(年に110万円)を超える部分について贈与税が課税されますが、住宅取得資金などの非課税の特例を利用すれば軽減できます。
ただし、ここでも省エネ性能の高い住宅とその他の住宅とでは、非課税限度枠に差が付けられています。
▼住宅取得資金等の贈与税の軽減の概要
| 住宅取得等に係る契約の締結日 | 2024年1月1日~2026年12月31日 |
| 質の高い住宅 | 1,000万円 |
| その他の住宅 | 500万円 |
非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「質の高い住宅」の要件については、ZEH水準(断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上)となっています。
※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、 現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。
▼床面積要件
50㎡以上
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。
▼非課税枠の併用
・暦年課税の非課税枠(110万円まで)との併用可
・相続時精算課税の非課税枠(2,500万円まで)との併用可
通常、直系の親族からの贈与にも基礎控除額である110万円を超えた金額には贈与税が課せられますが、住宅取得資金等の非課税の特例を利用すれば軽減できます。2025年度では、特例の非課税枠は質の高い住宅で1,000万円、それ以外の住宅でも500万円です。基礎控除額と併用すれば最大1,110万円までが非課税になります。
参照:国土交通省HP「https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf」
③新築住宅に係る住宅の減税措置延長(固定資産税)
新築住宅に係る固定資産税の減額措置が、2026年(令和8年)3月31日まで延長となりました。
▼固定資産税の特例措置の内容
| 新築住宅に係る税額の減額措置 | |
| 戸建て | 3年間 税額1/2を減額 |
| マンション | 5年間 税額1/2を減額 |
住宅用地など土地に関する固定資産税の負担調整措置および条例減額制度は2029年(令和11年)3月31日まで延長となりました。
また、「認定住宅等の新築をした場合の所得税額の特別控除」「工事請負契約書および不動産譲渡契約書の印紙税の軽減措置」「登録免許税の軽減」「不動産取得税の軽減」など、住宅の購入はもちろん、買い替えや持ち家のリフォームなど、多岐にわたる減税制度が、2024年に引き続き延長・実施されます。
制度をうまく活用して、新築住宅を購入しましょう。
≫過去の記事「新築住宅を購入するとかかる税金のはなし」
4)フラット35
【フラット35】とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。お申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設資金・購入資金または中古住宅の購入資金にご利用できます。
固定金利型のメリットは、資金受取時に返済終了までの金利と返済額が確定するため、たとえ市中金利や物価が上昇しても影響を受けない点です。これにより、将来の返済計画が立てやすく、安心感が得られることが変動型との大きな違いとなっています。
【フラット35】の内、機構が認める質の高い住宅に対して融資金利を優遇する制度です。
▽金利引き下げメニュー(2025年3月31日までの申込受付分に適用)
| 対象 | 期間 | 金利引き下げ幅 | 子育てプラス |
| 【フラット35】S(ZEH) | 当初5年間 | 年▲0.75% | 年最大▲1.0% |
| 【フラット35】S(ZEH)と長期優良住宅の併用で | 当初5年間 | 年▲1.0% | |
| 【フラット35】S(金利A) | 当初5年間 | 年▲0.5% | |
| 【フラット35】S(金利B) | 当初5年間 | 年▲0.25% |
2024年2月には、若年夫婦世帯や子育て世帯を対象とした【フラット35】子育てプラスが登場し、金利の引き下げ幅が最大年-1%に拡大されました。さらに、【フラット35】Sや地域連携型との併用も可能なため、固定金利型の安心感を活かした返済計画が立てやすくなっています。
エルハウジングの物件は【フラット35】基準をクリアしているため、多くのお客様にこの制度をご利用いただいています。なお、【フラット35】を利用するには、指定検査機関による「設計審査」と「適合証明書」の交付が必要となり、別途申請手数料が発生します。
参照:【フラット35】S HP「https://www.flat35.com/loan/flat35s/index.html」より
5)自治体の補助金・助成金
各自治体では、多様な補助金や助成金制度を提供しており、それぞれ条件や対象が異なります。利用を検討する際には、事前に内容を確認することが大切です。以下に代表的な補助金・助成金制度を紹介します。
①結婚・子育て応援住宅総合支援事業
新婚世帯の経済的負担を軽減するため、国や自治体が実施している「結婚新生活支援事業」をご存じでしょうか。この制度では、新居の購入費用や家賃、引越し費用などを補助することで、新婚世帯の新生活を支援しています。補助対象は、例えば新居の購入費、家賃、敷金や礼金、共益費、仲介手数料、リフォーム代金、引越し費用など、自治体によって異なります。京都府では、「新婚世帯スタートアップ支援事業」として、市町村と連携して支援を行っています。
エルハウジングが建売住宅を提供している滋賀県や大阪府でも、結婚助成金を受けられる地域がありますので、新婚世帯で転居や新築住宅の購入を検討中の方は、ぜひお住まいの自治体の支援制度を確認してみてください。
②多子世帯・三世代同居等推進支援事業
例えば京都府では、3人以上の子ども(妊娠中も含む)がいる世帯や親子・祖父母が同居、もしくは直線距離2キロメートル以内に居住する世帯を支援する「多子世帯・三世代同居等推進支援事業」を、市町村と協力して実施しています。この事業は、定住促進と少子化対策を目的としており、多子世帯や三世代同居・近居世帯に対して、住宅リフォームに必要な費用を最大100万円まで補助、住宅購入にかかる仲介手数料を最大40万円まで補助するなどの支援があります。また、京都府外から移住してきた世帯については、補助金が2倍となる市町村もあるので、詳しくはお住まいの地域の支援制度を確認することをお勧めします。
〈参照〉京都府HP「https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/news/jutaku.html」
制度の実施や対象等要件が年度ごとに変わる可能性もあります。事前に各自治体に確認してください。また、実施市町村ごとに内容が異なりますので、詳細は市町村担当窓口までお問い合わせください。
一時的な居住ではなく、あくまで定住や子育て世帯などが行う住宅のリフォームなどに必要な経費や住宅購入に必要な仲介手数料を予算の範囲内で補助するものであり、すべてのリフォーム工事や新築購入が該当するわけではありません。
③自治体の省エネ補助金
【京都府ZEH補助金】~令和7年2月21日 まで
京都府では、府内に自ら居住するために住宅を新築または購入する場合、「ZEH(ゼロエネルギーハウス)」「Nearly ZEH」「ZEH Oriented」を対象として、15万円の補助金を支給しています。
京都府内産材、北山丸太製品又は京銘竹製品を使用した住宅や、京都府の認証を受けた京都再エネコンシェルジュが設計した住宅は+25万円の補助金が支給されます。
参照:京都府ZEH補助金 令和7年度京都府住宅脱炭素化促進事業 補助金「https://www.kcfca.or.jp/project/2024zeh/」
【太陽光発電設備等の設置に対する助成】
京都市内では、住宅への太陽光発電設備や蓄電池の新たな導入を支援する制度「さんさんポイント」が開始されました。この制度は、太陽光発電を活用してCO₂排出量を削減することで得られる「環境価値」が、電子ポイントとして最大20万円相当還元されます。
|
導入支援
|
さんさんポイント |
|
太陽光発電設備や蓄電池等の導入支援
太陽光+蓄電池(V2Hを含む)をセットで設置した場合
|
20 万円相当 |
| 既存の太陽光に蓄電池(V2Hを含む)を追加で設置した場合 | 10 万円相当 |
この制度を利用するためには、「京都再エネクラブ」に入会する必要があります。発電した電気を家庭で消費することでポイントが還元されるため、エコでお得な仕組みとなっています。
参照:京都再エネクラブ「https://kyoto-repoint.jp/」
京都市の他にも例えば、京都府城陽市におきましても、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みが進められております。また、大阪府堺市では、住宅の脱炭素化を推進するため、太陽光発電システムの導入や「ZEH+(ゼッチ・プラス)」の要件を満たす場合に、費用の一部を補助する制度がございます。
建築物への太陽光発電設備導入・設置に関する支援制度は、お住まいの地域によって異なりますので、詳細はお住まいの自治体の制度をご確認いただくことをお勧めいたします。
まとめ
2025年度の補助金・助成金や減税制度に関しては、国や自治体の予算が決まり次第、その内容が発表される予定です。これから新築住宅の購入を検討している方は、最新の情報を逐次確認し、適用される支援制度や減税措置を見逃さないようにすることが重要です。特に、年度ごとに制度が変更される可能性があるため、計画的に利用できる補助金や減税を最大限活用するために、事前に最新情報をチェックすることをお勧めします。
注意点
| エルハウジングでは「省エネ基準適合住宅」に加え、より高い省エネ性能を持つ「ZEH水準」に適合する住宅を建築しています。
なお、上記でご紹介した補助金や減税制度が、エルハウジングの物件に適用されることを確約するものではありません。 (2025年1月現在) |
初年度は確定申告が必要
購入予定の物件が補助金・助成金制度の条件を満たしたとしても、漫然と減税が受けられるわけではなく、確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の源泉徴収で減税が受けられますが、初年度はご自身で確定申告を行ってください。
≫関連記事「2030年までに義務化。ZEH水準の省エネ住宅とは?」
≫関連記事「2025年より義務化。省エネ基準適合住宅とは?」
※こちらの記事は2024年12 月現在の情報をもとにしてます。
![]() 「
補助金や制度 」の最新記事
「
補助金や制度 」の最新記事





